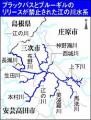2007年2月15日Japan Official Fishing Instructor Hiroshima
発行者/釣りインストラクター連絡機構事務局
平成18年度広島県海面利用協議会報告
「遊漁者のまきえ釣りに対する規制の一部解除について」
◆ 日時:平成19年1月29日(月)10:00~
◆ 場所:広島海区漁業調整委員会委員室
◆ 出席者:<委員>
広島市漁業協同組合・代表理事組合長・濱本会長(漁業代表)、深江漁業協同組合・代表組合長・樋口委員(漁業代表)、尾道漁業組合・代表理事組合長・大胡委員(漁業代表)、全日本サーフキャスティング連盟広島協会・会長・蔦委員(遊漁代表)、広島県釣りインストラクター連絡機構・代表・岡田委員(遊漁代表)、広島県釣り団体協議会・事務局長・土屋委員(遊漁代表)、(社)瀬戸内海海上安全協会・常務理事・近藤委員(海レク代表)、中国マリン事業協会・理事・花野委員(海レク代表)、(財)広島県漁業振興基金・専務理事・清水委員(学識経験者)、(財)日本船舶職員養成協会・中国支部長・熊崎委員(学識経験者)。
<オブザーバー>
広島県地域事務所農林水産課・水産振興係長・堀田氏、呉地域事務所農林局農村振興課・水産振興係長・廣中氏、東広島地域事務所農林局農村振興課・水産係長・木田氏、尾三地域事務所農林局水産課・主任・島田氏、福山地域事務所農林局水産課・課長・萩田氏。
<事務局>
広島県農林水産部漁業調整室・室長・西本氏、主任主査・紙本氏、主任・米山氏。
◆議題
「遊漁者の行う陸からのまきえ釣りに対する規制解除(案)について」
1 案の概要
(1) 遊漁者にたいして全ての「まきえ釣り」を禁じている現行の広島県漁業調整規則を一部改正して、陸からの同漁法を解禁する。
(2) 船から行うまきえ釣りについては、遊漁者への規制を継続する。
(3) 一本釣りの重要漁場や幼稚魚の育成場等、特に規制が必要な水面については、漁業者、遊漁者を問わずまきえ釣りを禁止する海区委員会指示の発動を依頼する。
2 理由
(1) 平成13年に制定された「水産基本法」では、増加する遊漁者と漁業者との共存が向されている。それを踏まえて平成14年12月12日付けで都道府県調整規則例の一部が改正され、遊漁に対する過度あるいは一方的な規制を防ぐ観点から、遊漁者にもまきえ釣りを認める内容とされた。(①まき餌釣漁法の解除???現在、規則例第51条第1号においてまきえ餌釣りは遊漁者には認めない漁法として例示されているが、実態としては沿海都道府県の約半数の規則において既に規制されておらず、全国的にもまき餌釣は遊漁船の主要な営業種目となっているほか、海釣り公園などでも用いられている等、一般的な漁法として、定着している実態がある。また、こうした遊漁の実態が漁業との間で大きなトラブルとなった事例は近年ではほとんど見受けられず、遊漁者に対して禁止漁法として制限する必要性は一般的に認められなくなっている。このため、規則例第51条第1号を改正し、漁業以外の場合に認められる漁法にまけ餌釣を認めることとする。なお、本件規則例改正を踏まえて規則改正を行う際に、都道府県ごとの実状により、特定の区域を区切り、まき餌釣漁法の禁止区域として別途規定することも考えられる。
(2) 船を利用したまきえ釣りを行う場合、多くはイカリを下ろして長時間漁場を占有するため、漁業の操業に支障をきたしている事例が数多く報告されている。また、漁業者に対しても船舶を利用したまきえ釣りは許可制として規制しており、資源保護及び漁業との調整上、遊漁者への規制を継続する。
(3) 一本釣り漁業の漁場の多くは「まきえ釣り」と競合するため、その影響を最も受けやすい。特に、釣り専業者ほど漁獲物の品質と鮮度の良さで他漁法との差別化を図っており、重要な漁場は保護すべきである。また、放流魚をはじめとする幼稚魚の保護育成の取り組みが行われている場所では、地元漁業者は一定期間禁漁を行う等の自主規制を行っており、遊漁者や他地区漁業者の協力が望まれる。
3 経緯
平成14年の都道府県漁業調整規則例の改正を契機に、海区漁業調整委員会での検討が重ねられた結果、概ねこの案で承認された。(遊漁者に対するマナー向上の啓発活動を充実するよう意見が付された。全国の状況をみても、全面的に遊漁によるまきえ釣りを禁止しているのは沿海40都道府県中11都県に過ぎず、特に隣接する岡山県(船舶使用禁止)、香川県(船舶使用禁止)及び山口県(漁法について委員会指示)でも遊漁者によるまきえ釣りが一部可能となっている。
4 広島県漁業調整規則改正案
改正案 現行
(遊漁者などの〔※1〕漁具漁法の制限) (非漁民等の漁具漁法の制限)
第48条漁業者が漁業を営むためにする 第48条 漁業者が漁業を営むためにする
合若しくは漁業従事者が漁業者のために 場合若しくは漁業従事者が漁業者のために
従事してする場合又は試験研究のために 従事してする場合又は試験研究のためにす
する場合を除き、水産動植物を採捕する る場合を除き、水産動植物を採捕する場合
場合は、次に掲げる漁具又は漁法によら は、次に掲げる漁具又は漁法によらなければ
なければならない。 ならない。
(1) 竿釣及び手釣(船舶を使用して行 (1)竿釣及び手釣(まきえ釣りを除く。)
まきえ釣を除く。(※2)
(2) たも網及び手網(船舶を使用しな (2)たも網及び手網(船舶を使用しない
いものに限る。) ものに限る。)
(3) 投網(船舶を使用しないものに限 (3)投網(船舶を使用しないものに限る。)
る。)
(4) は具、やす(ゴム又はばね等によ (4)は具、やす(ゴム又はばね等により
り発射するものを除く。) 発射するものを除く。)
(5)(一部削除〔※3〕)徒手採捕 (5)歩行徒手採捕
前項規定により水産動植物を採捕する 前項の規定により水産動植物を採捕する
場合は、正当な漁業の操業を妨げない 場合は、正当な漁業の操業を妨げない
ようにしなければならない。 ようにしなければならない。
(※1)用語の習性。(国の模範例改正に準拠。)
(※2)全てのまきえ釣りを除外している現行規則を、「船舶を使用して行う」もののみ除外するよう改正する。(陸からのまき餌釣りを解禁する。)
(※3)明確な表現に修正。(国の模範例改正に準拠。)
・との提案に対して、予め1月11日に委員からの提案を求められていたので、関係者の皆さんに意見聴取を致しました。そして、数名の方からのご意見により、次のような意見を提出いたしました。
<委員提出事項>
【提案】(提出委員 岡田敏孝)
題名:「まきえ釣りの一部規制解除容認に係わる海区漁業調整委員会の付帯意見について」
内容:「議題1の検討の際、陸からのまきえ釣りの規制解除を容認するに当たり海区漁業調整委員から示された“付帯意見”の内容を提示していただきたい。」
<付帯意見>
「遊漁者に対するまきえ釣りの規制解除については、漁業操業や遊漁実態及び隣県の状況さらには時代の要請等を踏まえて総合的に判断した結果、陸からのまきえ釣りについては、漁業者の立場を考えた場合、大いに不満ではあるが、苦渋の選択として解除もやむを得ないという結論に至った。
なお、陸からのまきえ釣りを解除を容認するに当たり、県に対して次の対応策を講ずるよう付帯意見を付することた。
1 漁業者と遊漁者とのトラブル防止を図るため、遊漁者への啓発・指導の徹底と取り締まり強化に努めること。
2 共同漁業権の第3種及び第4種が設定されている海域であって、その範囲が陸に接している海域及び育成水面や稚魚の港内飼付を行っている海域では、陸からのまきえ釣りを制限すること。また、これ以外の海域においても新たな問題が発生した場合には、制限を検討すること。
3 遊漁者の船舶を使用してのまきえ釣りについては、規制を継続すること。
4 遊漁者による碇を打って船を係留しての船釣りについては、規制を検討すること。
<釣りをするのに制限される区域(海)>
釣りをするのに制限される区域は、広島県の海面にはつり漁業を対象とした漁業権(第3種、第4種共同漁業)がおよそ次のように設定されています。
「これらの区域では、地元の漁業者が一定のルールに従って、生活の糧を得るため操業を行っています。たとえ手釣り、竿釣りであってもこれらの区域では勝手にできませんし、漁業権を侵害することにもなりかねません。」
●保護水面における採捕の禁止(広島県漁業調整規則第34条の2)次の海面においては、水産動植物の採捕は一切禁止されています。
・ 豊田郡大崎上島町生野島南西側海面
・ 呉市倉橋町黒島東側海面
◆ 第3種、第4種共同漁業権設定区域(別紙参照)
◆ 保護水面(釣り等一切禁止区域)<別紙参照>
【提案】(提案委員 濱本隆之)
題名:漁業者と遊漁者のトラブル
内容:漁業者が操業している時に、遊漁者の船に妨害されるときがあり、特に広島湾ではカキ筏に無断であがったり、養殖しているカキを勝手に取って餌やまき餌に使用する事例が増加している。県に後者について通報した際、窃盗であり海上保安部に相談するよう言われたが、連絡調整はできないのか。
〔意見交換〕
漁業者:陸釣りと船釣りの区別と取締りをしてほしい。また、解除の広報を徹底してほしい。
漁業者:海区委員会に対して、基本的には反対であることを伝えてほしい。
学識経験者:海区委員の立場から、常識的な対応なのではないか。
学識経験者:遊漁者の啓発を担当しているが、取締りをどうするのか。
海レク代表:船舶の定義、船釣りに限定すると取り締まりやすい。元海保にいたものしては。
遊漁代表:第3種、第4種共同漁業権設定区域が示されたが、一般釣り人はほとんど認知していないのが現状。広島県釣りインストラクター連絡機構としても各港湾なで「海面釣り場調査」や「釣り教室」などでルールやマナーとして指導していますが、この際衆智徹底する方法を考えていただきたい。
また、片アンカーまでの船釣りを禁止したら、航路への侵入、他船との衝突などの重大事故の危険性が考えられますが。
遊漁者代表:報道関係で、解除について広報していただきたい。
農林水産部漁業調整室:(取り締まり強化について)
調整室取締りグループで担当している。また、「取り締まり船」でポスター配布したり、資料配布などして、指導はしている。が検挙などの取り締まりはできない。
(海区域の規制について)
海区委員会の指示の形で毎年更新している。
(「碇」について)
・ まきえ釣りを想定している。
・ 両アンカーは禁止。
・ 片アンカーは方向が分からなく、支障が大きい(底引き網船など)。
・ 碇????地磯の魚を絶やすので禁止。
(船釣りのまきえ釣り禁止)
・ 釣り筏は例外・許可
・ 県の広報で情宣する。
(広報について)
ホームページで実施しているが、各団体による情宣をお願いしたい。
海面利用協議会委員:・マスコミなどに映像で流してほしい。
・ 釣具手での広報やマキエ(船釣りの)販売禁止を>
・ 釣り人手帳(他県)や下敷き(漁協)等の配布してほしい。
・ 船舶手帳に掲載していただきたい。
などの論議が行われ、次回「海区委員会」に付託するところとなる。
投稿者: jofi/JOFI広島事務局会報
「遊漁者のまきえ釣りに対する規制の一部解除について」 はコメントを受け付けていません。