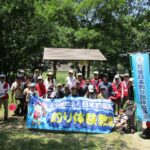日時:令和7年9月6日(土) 9時~15時
会場:錦川漁業協同組合会議室 & 錦川の南桑
受講者:15名(山口8名、広島7名)
講師:太田博文氏、平田洋司氏、三角政志氏、他8名
主催:錦川漁業協同組合
協賛:(公財)日本釣振興会中国地区支部、JOFI広島、広島清流会、
㈱シマノ、㈱サンライン、㈱マルト
内容
前日の雨模様から一転、晴天の中、岩国市の錦川漁協主催の鮎釣り教室の講師として参加。受付を済ませた15名の受講生が席について、組合長から挨拶があり、(公財)日本釣振興会山口県支部長の挨拶後、講師の紹介があり、JOFI広島・太田会長による講義が約45分あった。
宇佐川の鮎釣り教室(8/2)にも参加した方が数名いたため、少し高度な鮎釣りの講義に変更。苔の話では、珪藻と藍藻の違いとその効果の違い。それに関連した鮎の縄張り行動の理由、鮎の種類の違い、海外をはじめ台湾や韓国の鮎釣り事情などを織り込み日本との違いを説明した。道具では、曳舟、鮎竿などを見せ指導を行った。講義後、仕掛教室で周りに集まってもらい、ハナカン周りの仕掛け作り、天井糸仕掛、水中糸仕掛、チラシのハリ仕掛、三本イカリ仕掛、ハナカン仕掛と水中糸の強度の落ちない結束方法、天井糸仕掛との結束方法など、目の前で作りながら説明、出来た仕掛けを手に取って見てもらった。質疑応答の後、昼食。
実釣の場所には、組合員の先導で各自の車両で移動。各自着替えを終えテント前で記念撮影。その後、担当者別に分かれて個別指導を開始。まず、オトリ鮎の持ち方、ハナカンの通し方、一皮サカサの打ち方、オトリ鮎の放す方向、目印の位置を参考にした竿の角度の調整法を指導した後、竿を受講者に渡し釣り開始。岸から入り込まず泳がせて沖へ誘導。中々難しい技ですが、指導をよく聴講したせいか泳がせていると一気に目印が飛び野鮎が掛かった。
オトリ交換後に2匹掛け合計3匹掛けた。途中、カヌー下りが4艘漕いできて、竿先にサドルで水面を漕いでいるので、サドル操作をしないよう声を掛けた。15時集合で釣果は最高で7匹掛けていた。受講者から、広島でもこのような教室がないだろうかと尋ねられたが、残念ながら漁協組合の協力がないと、日券代、オトリ代、講師料の費用が負担になるため、今は開催していないとしか返答できなかった。事故やケガもなく、大きな天然鮎(25cm)も釣れた錦川鮎釣り教室でした。
報告者:太田博文氏
投稿者: jofi/錦川鮎釣り教室 はコメントを受け付けていません。