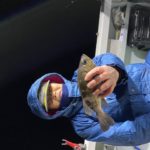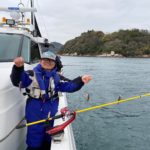日時 令和2年6月21日(日)午前8時30分~正午 晴れ
場所 広島市安佐北区可部町今井田 柳瀬キャンプ場太田川 河川敷左岸
参加者 4家族、保護者4人、子供6人、スタッフ・講師12人、計22人
参加費 500円(1家族)、エサ代他
主催 公益財団法人 広島市文化財団 日浦公民館
協力 広島県釣りインストラクター連絡機構、公益財団法人 日本釣振興会広島県支部
講師 村上氏、田辺氏、平田氏、冨樫氏、中木氏、三角氏、柳原氏、佐々木氏



内容
例年どおり、釣り場清掃と草刈りを6月15日(月)に行った。日浦公民館より新谷館長と向井主事、佐東公民館より樋口館長と弘中主事の4人の方にもご協力いただき、公認釣りインストラクター中木氏、平田氏、冨樫氏、村上氏、佐々木氏の9人で、8時から10時頃まで一年間伸びた草を電動草刈機2台、剪定鋏や鎌を使い、炎天下のもと、何とか釣りができる状態にした。
6月13日(土)の雨でかなり増水していたが、昨夜のうちにだいぶん水が引いていたのでハヤが釣れるか試し釣りをした。結果、型の良いオイカワが釣れ、当日雨の降らないことを願い解散。



当初6月20日(土)に釣り教室を計画していたため、前日19日(金)16時頃村上氏と現地を視察。心配したとおり17日(水)夜から18日(木)の雨で釣り場が全部浸水していた。急遽、公民館へ引き返し、新谷館長と向井氏を交えて対策を練る。結果、止むなく1日延期し21(日)に実施することに決定。公民館では急いで参加者に連絡し、自分は釣りインストラクターたちに連絡をした。



幸いに当日は天候にも恵まれ、昨夜のうちに水も引き何とか釣り教室ができる状態だったので、早速全員で準備に取り掛かった。釣り場へ道具やテントを運び事前にマキエを打ち釣り場の準備をする。受付・座学会場には幟を立て、机などを用意する。キャンプ場内の釣り教室で、土日にかけてのキャンパーが大勢おられ、テントや車が多かったのには少し驚いた。一部の方に訳を話しテントや車を移動してもらった。ご協力ありがとうございました。



8時30分より向井主事と柳氏の司会進行で受付を開始。延期したため2家族が欠席し、4家族が揃ったところで釣り教室を開始した。はじめに日浦公民館より挨拶があり、講師紹介のあと、冨樫講師よりハヤ釣りに関する色々な話を、日釣振提供の「好き好きフイッシング」の教本に基づき行った。
川で釣れる魚、今日釣るオイカワやカワムツ等写真を見せ、竿や仕掛けの扱い方、投げ方、エサの付け方、また一番大切なマナーやルールを守り安全な釣りをするよう座学をした。また、講師の指導により安全を期し全員にライフジャケットを着用し釣り場へ移動。
釣り場でも再度、講師がマンツーマンで指導に当たり、準備のできた者から竿を出した。マキエの効果は抜群で、一投目から美しいオイカワが釣れ、親子の楽しい釣りが始まった。結果、全員がハヤを釣ることができ、釣ったハヤをカメラに収めている親子の姿は、なんともほほえましい光景であった。



11時30分納竿、事前に渡した火ばさみとゴミ袋を持ち全員でゴミを拾い会場へ集まった。子どもたちはアンケートを記入し、閉会式では中木講師の講評、佐々木講師からの延べ竿のプレゼント、全員の集合写真を撮り、向井主事の閉会の言葉を最後に解散した。何はともあれ、何事もなく無事終了した事を報告します。たくさんハヤも釣れ、子どもたちも、来年また釣りに来たいと口々に言っていた。熱心に指導していただいた釣りインストラクターの皆さまに、厚くお礼を申し上げます。
報告者:佐々木晃二郎氏
投稿者: jofi/親子ハヤ釣り教室 はコメントを受け付けていません。